資格
- 日本消化器外科学会 認定医
- 日本外科学会 認定医
- 日本医師会 認定産業医
睡眠時無呼吸症候群は睡眠時呼吸障害の1つです。睡眠時に症状が起きるため、ご自身では気付きにくい特徴があります。睡眠時に呼吸が止まることで睡眠の質が下がるため、集中力の低下や倦怠感を抱きやすいなど日常生活において支障をきたすリスクが高まります。
また、心筋梗塞や高血圧などの合併症を発症する恐れもあるため、早めに適切な治療を受けることが大切です。
本ページでは、睡眠時無呼吸症候群の症状や治療法、ご自身でできる予防法を紹介しています。睡眠時無呼吸症候群の症状が当てはまる方は、早めに医療機関を受診することをおすすめします。
-
日本内科学会 認定内科医が在籍
-
CPAP治療にも対応可能
-
女性医師が在籍
-
土曜日も診療可能
睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは
睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは、睡眠時に呼吸が止まってしまう病気です。「Sleep Apnea Syndrome」の略からSAS(サス)とも呼ばれます。10秒以上呼吸が止まっている状態が7時間の睡眠中に30回以上、もしくは1時間に5回以上起こる際に、睡眠時無呼吸症候群と診断されます。
睡眠時に繰り返し呼吸が止まるため、熟睡できず日中に眠気を感じたり、倦怠感や疲労感を抱いたりすることが多いのですが、ご自身が睡眠時無呼吸症候群であることに気付いていない方も少なくありません。
主な症状
健康的な生活をおくるためには睡眠が欠かせません。睡眠中に身体を休める必要があるからです。
しかし、睡眠時無呼吸症候群になると、継続して睡眠時の呼吸が止まるため、体の酸素が減少してしまいます。
酸素が減少すると心拍数が上がり身体にも負担がかかります。寝ている間に身体に負担がかかっている状態は、十分に身体を休めることができず、起床時に疲労感を感じたり、日中に眠気に襲われたりする症状が生じるでしょう。
その結果、日常生活に支障をきたす恐れもあるため注意が必要です。
以下のような症状がある方は、睡眠時無呼吸症候群である可能性があります。
- いびき
- 日中の過度な疲労感
- 集中力の低下
- 起床時の頭痛
- イライラなど感情的不安感
いびき
いびきは気道が狭くなることで生じる音です。空気の通り道となる気道が狭くなると呼吸がしづらくなり、無呼吸を引き起こしやすくなります。慢性的にいびきをかいている方は、睡眠時無呼吸症候群である可能性が高いでしょう。
まだ発症していない場合も、いびき症状がある方は睡眠時無呼吸症候群を発症するリスクが高いといえます。
睡眠時無呼吸症候群を伴ういびきの特徴は、いびきが一時停止した後、激しいいびきが再開します。
いびきは同居者に確認しやすい症状であるため、睡眠時のいびきの音を録音してもらい、診察時に医師に提出するのもおすすめです。
日中の過度な疲労感・過度な眠気
睡眠時無呼吸症候群の代表的な症状の1つに、日中の過度な疲労感や眠気があります。睡眠時に呼吸が止まっていると、寝ている間に身体を休めることができないため、疲れが取れず疲労感が現れます。
睡眠の質が低下するために、日中に過度な眠気に襲われることも少なくありません。
このような疲労感や眠気は、仕事や学業の妨げになることも多いため、早めの改善が必要です。
集中力の低下
睡眠時無呼吸症候群の状態が続けば続くほど、集中力も低下しやすい傾向にあります。呼吸が止まることで熟睡できないために睡眠不足の状態となるためです。集中力の低下で特に気をつけたいのが、車の運転などの行為です。
集中力が低下している状態の運転は、交通事故を引き起こす危険もあります。集中力が低下していると感じる場合は、車の運転は避けるようにしてください。
起床時の頭痛
起床してから数時間程度、頭痛症状が現れることも多くあります。これは、睡眠時に呼吸が止まっていることで酸素が不足し、脳の血管が拡張することで起こる症状です。睡眠時無呼吸症候群が原因で頭痛を引き起こしている場合は、通常数時間程度で治ります。
長時間頭痛が治らなかったり頻繁に頭痛が生じたりする場合は、他の原因も考えられますので、検査を受けたほうがよいでしょう。
イライラなど感情的不安感
睡眠不足や質の悪い睡眠は、身体的な問題だけでなく、心理面にも影響を及ぼします。「疲労感がとれない」「熟睡したいのに目が覚めてしまう」などの理由からイライラすることも多いでしょう。
そのほかにも、睡眠不足の状態はストレスホルモンの分泌が増加するため、感情が不安定になったりうつ症状が現れたりする可能性もあります。
睡眠時無呼吸症候群の原因
睡眠時無呼吸症候群には、「閉塞性睡眠時無呼吸」と「中枢性睡眠時無呼吸」の2種類があります。
それぞれの種類によって原因は異なります。ご自身の睡眠時無呼吸の状態を把握するためにも、それぞれの睡眠時無呼吸について理解しておくとよいでしょう。
閉塞性睡眠時無呼吸
閉塞性睡眠時無呼吸とは、上気道の閉塞が原因で起こる睡眠時無呼吸です。睡眠時無呼吸症候群を発症している方の多くがこの「閉塞性睡眠時無呼吸」です。
日本国内には、閉塞性睡眠時無呼吸の患者が900万人以上いると推定されていますが、そのうち治療を受けているのは50万人に満たないといわれています。
それほど自覚症状がなく、自分では気付きにくい病気です。
肥満
肥満は気道が狭くなり閉塞性睡眠時無呼吸を発症しやすくなります。首元に脂肪がついている方は特に気道が閉塞しやすいために、閉塞性睡眠時無呼吸のリスクが高まります。
肥満が原因で閉塞性睡眠時無呼吸を発症している方は、減量することで症状が改善する可能性もあるでしょう。
身体の構造的な問題
扁桃腺が肥大していたり、鼻中隔が湾曲していたり、元々の身体の構造が原因で気道が狭くなり、閉塞性睡眠時無呼吸を発症するケースもあります。この場合は、手術で構造の問題を解消することで、閉塞性睡眠時無呼吸の改善にもつながります。
扁桃腺の肥大は子どもに多くみられる症状です。扁桃腺肥大の疑いがある場合は、早めに耳鼻咽喉科を受診し適切な治療を受けるようにしましょう。
加齢
加齢とともに閉塞性睡眠時無呼吸のリスクは高まります。加齢によって咽頭部の筋肉が衰えることが主な原因です。そのため、中年以降の方は肥満体型でなくても閉塞性睡眠時無呼吸を発症しやすくなります。
筋力アップのための運動を取り入れたり、定期的に健康診断を受診したりすることで閉塞性睡眠時無呼吸の予防につながります。
中枢性睡眠時無呼吸
中枢性睡眠時無呼吸とは、脳の呼吸中枢がうまく機能しないことが原因で起こる睡眠時無呼吸です。脳には呼吸を調整する呼吸中枢がありますが、この呼吸中枢に異常があることで、気道が閉塞を伴わないのに睡眠時に呼吸が止まってしまいます。
心臓疾患
心不全など心臓疾患がある方の30〜40%に中枢性睡眠時無呼吸がみられるといわれています。心臓に血液を供給できていないと、脳へ酸素を供給するのも不足してしまうためです。
心臓疾患が原因で中枢性睡眠時無呼吸を発症している方は、心臓専門医と連携した治療が必要になります。
脳の疾患
脳腫瘍や脳卒中などの脳の疾患が原因で、中枢性睡眠時無呼吸を引き起こすことがあります。脳の疾患によって、呼吸をコントロールする信号がうまく伝達されないことがあるためです。
脳の疾患が原因で中枢性睡眠時無呼吸の症状がみられる方は、まずは脳外科で精密検査を受けたほうがよいでしょう。
特に脳卒中を発症した方は、適切な管理を行うためにも経過観察が欠かせません。
睡眠時無呼吸症候群の治療法
睡眠時無呼吸症候群の主な治療法は以下の3つです。
- CPAP(持続陽圧呼吸療法)
- マウスピース
- 外科手術
睡眠時無呼吸症候群の原因や、症状の程度によって適切な治療法は異なります。
CPAP(持続陽圧呼吸療法)
CPAPとは持続陽圧呼吸療法とも呼ばれます。睡眠時の気道を拡げるために、専用の装置を用いる治療です。CPAP装置によって鼻から空気を送り続け、気道に一定の圧力をかけて、気道が開いた状態を維持します。
重度の睡眠時無呼吸症候群の方に行われる治療法であり、専門医の指導のもと使用する必要があります。
マウスピース
睡眠時無呼吸症候群の症状が軽度である場合は、マウスピースを用いた治療を行います。マウスピースを装着することで、就寝時に下顎が前に出て、舌の位置が下がらず気道を確保しやすくすることが目的です。
睡眠時無呼吸症候群のマウスピースは市販でも入手できますが、歯科医院で作成することをおすすめします。
歯科医院では型取りをしてマウスピースを作成するため、一人ひとりの口腔内に適したマウスピースが仕上がり、より効果的な治療が期待できます。
外科手術
気道を拡げるために行われる手術であり「気道拡張手術」とも呼ばれます。睡眠時無呼吸の原因を解消するための外科手術です。睡眠時無呼吸の原因は一人ひとり異なるため、患者さまの状態によって手術内容は異なります。
扁桃腺が原因である場合は扁桃腺摘出術が行われたり、鼻中隔が湾曲している場合は鼻中隔湾曲矯正術で鼻の通りを良くしたりします。近年では、切開せずに済むレーザー治療も導入されているので、手術方法については医師と相談するとよいでしょう。
睡眠時無呼吸症候群の対処法
軽度の睡眠時無呼吸症候群である場合は、ご自身のケアによって改善ができるケースもあります。
症状が悪化しないためにも、以下の方法を取り入れて予防しましょう
体重管理
肥満は睡眠時無呼吸症候群のリスクが高まります。首元に脂肪が蓄積することで気道が狭くなるためです。体重管理を行い、健康的な体型をキープすることで睡眠時無呼吸症候群の改善が期待できます。
アルコールや喫煙の制限
アルコールや喫煙によって睡眠時無呼吸の症状が悪化することがあります。アルコールは咽頭部の筋肉を緩めるために気道が狭くなりやすく、喫煙は気道の炎症を引き起こす恐れがあるためです。アルコールや喫煙を控えることで、これらのリスクを回避でき、睡眠時無呼吸の症状の緩和につながります。
また、アルコールや喫煙は睡眠の質も低下しやすいことが明らかになっているため、良質な睡眠をとるためにもアルコールや喫煙を控えたほうがよいでしょう。
睡眠の質の向上
良質な睡眠をとるためには、睡眠時の環境を整えることが大切です。ストレスを溜めないよう心がけたり、枕などの寝具にこだわったりすることで睡眠の質が変わります。また、睡眠時無呼吸症候群の方は、就寝時の姿勢にも気をつけましょう。
仰向けの姿勢で寝ていると舌の位置が下がって気道が狭くなる傾向にあるため、横向きで寝ることをおすすめします。
当院の睡眠時無呼吸症候群治療の特徴
睡眠時無呼吸症候群は自覚症状が少ないためにご自身では気付きにくく、適切な治療を受けていない方が多い病気です。適切な治療を受けていないと、睡眠の質が低下するだけでなく、心臓や脳に負担がかかりさまざまな疾患を発症する原因にもなります。当院では、専門医による指導が必要なCPAP治療が可能です。
CPAP治療は副作用がほとんどありません。重度の睡眠時無呼吸症候群の方にも対応できる治療法です。
「熟睡できない」「家族にいびきを指摘された」など睡眠時無呼吸症候群の症状が当てはまる方はお気軽にご相談ください。患者さまに適した治療法を提案いたします。
睡眠時無呼吸症候群の診断方法
睡眠時無呼吸症候群の疑いがある場合は、まず問診で睡眠尺度評価を行ってから、スクリーニング検査を実施します。スクリーニング検査は自宅でできる簡易検査で、パルスオキシメータ法と簡易式ポリソムノグラフィー(PSG)があります。
| パルスオキシメータ法 | 指先にセンサーをつけて、一晩中、血中の酸素飽和度と脈拍数を測定し、無呼吸による酸素の低下状態を調べます。 |
| 簡易式ポリソムノグラフィー(PSG) | 携帯型装置を睡眠時に装着し、睡眠中の酸素飽和度や心拍数、呼吸状態を調べます。心電図や体動などを調べられる機器もあります。 |
スクリーニング検査だけで睡眠時無呼吸と診断されることもありますが、さらに詳しい検査が必要と判断された場合は、1〜2泊入院をして精密検査を行います。精密検査では、脳波・心電図・呼吸・血中酸素・筋電図などを詳しく調べます。検査結果をもとに、閉塞性睡眠時無呼吸化と中枢性睡眠時無呼吸のどちらなのか、睡眠の質や不整脈の有無などもチェックします。

地域に寄り添い、79年。

専門医複数名
在籍

下館駅から徒歩4分
駐車場完備

土曜日
12:30まで診療
-
日本消化器外科学会 認定医,日本外科学会 認定医,日本医師会 認定産業医,日本医師会 認定健康スポーツ医 大圃 弘
-
日本外科学会 外科認定医,日本外科学会 認定登録医,日本医師会 認定産業医 大関 美穂
-
日本内科学会 認定内科医 大圃 研,根岸 良充,伊藤 洋平
茨城県筑西市にある大圃クリニックは日本内科学会 認定内科医が在籍でCPAP治療にも対応しています。
下館駅北口から徒歩4分で駐車場20台完備。土曜日も診療可能です。
睡眠時無呼吸症候群は、集中力の低下や倦怠感を抱きやすいなど日常生活において支障をきたすリスクが高まります。
また、心筋梗塞や高血圧などの合併症を発症する恐れもあるため、早めに適切な治療を受けることが大切です。
記事の執筆・監修者プロフィール
1946年(昭和21年)に父が『大圃外科医院』を開院し、約70年にわたり、入院・手術の出来る病院として、地域医療に取り組んで参りました。
1967年には『大圃病院』、1994年に『大圃クリニック』と名称と診療体制を変更し、今まで同様に多くの患者様にご来院いただいております。
これからも患者様一人ひとりの健康と快適な生活を支えることを最優先に考え、地域社会に寄り添った診療ができるよう身近なかかりつけ医を目指して参ります。
資格
- 日本消化器外科学会 認定医
- 日本外科学会 認定医
- 日本医師会 認定産業医








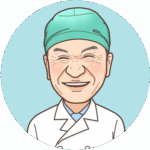












大圃クリニック院長
大圃 弘
睡眠時無呼吸症候群で気をつけたいのが合併症です。呼吸が止まることで睡眠時に酸素が不足し、心臓や脳、血管などへの負担が大きくなります。その結果、心筋梗塞や高血圧、脳梗塞などの合併症を発症するリスクも高まるため、早めに適切な治療を受けることが重要です。