資格
- 日本消化器外科学会 認定医
- 日本外科学会 認定医
- 日本医師会 認定産業医
咳が長引いたり、息苦しさを感じたりした時に医療機関を受診すべきか迷われている方も多いでしょう。
このような症状は呼吸器にトラブルがある可能性があるため早めに受診しましょう。
-
日本内科学会 認定内科医が在籍
-
ワクチン接種、健康診断にも対応可能
-
女性医師が在籍
-
土曜日も診療可能
大圃クリニックの呼吸器疾患治療
当院の呼吸器疾患治療では、患者さまの健康を維持するために治療はもちろんのこと、予防から治療後の管理までを行っております。
呼吸器疾患には、肺炎や気管支炎などの疾患があり、受診のタイミングが遅れて重症化してしまうケースがあります。
そのため、早期発見・早期治療が重要です。
例えば、「咳が出ているけど、ただの風邪だろう」と放置していると、実は風邪ではなく喘息だったり肺炎をこじらせていたりするケースも少なくありません。
生きていくために呼吸は欠かせないものです。
臓器を損傷する前に適切な治療を行えるよう、当院でサポートいたします。
また、当院では肺の状態を確認するため、スパイロメトリー(肺機能検査)にも対応しています。
スパイロメトリーは5〜10分程度の短時間で実施できる検査であり、食事制限も痛みもないため、患者さまの負担が少ない検査方法です。
このような症状がある方はご相談ください
呼吸器に問題がある場合は、咳や痰が出たり、ゼーゼーした呼吸音になったりと音の異常が現れやすい傾向にあります。
呼吸がうまくできない状態に陥ると、息切れや息苦しさを感じたり、チアノーゼが出現したりします。
呼吸に関する疾患は、命に関わるケースもありますので、以下のような症状がある方は早めの受診をおすすめします。
呼吸器疾患で受診したほうがよい症状
- 咳
- 痰
- 血痰
- 息苦しさ
- 胸の痛み
- 背中の痛み
- 発熱
- いびき
- 日中の強い眠気
- ゼーゼーした呼吸
よくある呼吸器疾患
主な呼吸器疾患
- 風邪症候群
- インフルエンザ
- 咳喘息
- アスリート喘息
- 気管支喘息
- 気管支炎
- 肺炎
- 気管支拡張症
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD/肺気腫・慢性気管支炎)
- 肺結核
- 気胸
- マイコプラズマ肺炎
- 呼吸不全
- 肺がん
気管支喘息
気管支喘息とは、一般的に喘息と呼ばれる病気のことです。
アレルギーやウイルス感染などによって気管支に炎症を引き起こすことで発症します。
気管支に炎症が起こると少しの刺激が加わるだけでも気道が狭くなり、息苦しさを感じたり咳が出たりする発作が生じます。
気管支喘息はこの気管支の炎症が慢性化しているため、症状が出ていない時にも常に気管支が炎症を起こしている状態です。
主な症状 |
・早朝や夜間に激しい咳が出る
・ヒューヒューという呼吸音
・風邪症状が治っても咳だけが長引く
・呼吸が苦しい
|
検査方法 |
・血液検査
アレルギーが原因で気管支喘息を発症していることがあるため、血液検査によってアレルギーの評価を行います。
・スパイロメトリー
スパイロメトリーとは肺機能検査のことです。
気道の状態を数値やグラフで評価することが可能です。
・呼気NO検査
呼気の一酸化窒素濃度を測ることで炎症の程度を調べる検査です。
気道の炎症によって吐いた息はNO(一酸化窒素)が上昇する特徴があります。
この検査は、診断時だけでなく、治療効果を調べるためにも用いられます。
|
治療方法 |
吸入治療を中心に、必要に応じて気管支拡張薬の使用や自己管理(吸入手技・アレルゲン回避・呼吸リハ)を行う
|
咳喘息
咳喘息は、咳が長引く症状が出る病気です。
一般的な喘息とは異なり、「ヒューヒュー」「ゼーゼー」といった喘鳴は伴いません。
咳喘息の場合、アレルギーによって気管支に炎症が起こりますが気管支自体は狭くならないからです。
ただし、悪化すると気管支喘息へと移行するため、適切な治療が必要です。
治療方法は、症状の程度によって異なりますが、中等度以上であればステロイドと気管支拡張薬の合剤を用いた治療を行います。
症状が軽快したからといって治療を中断すると、再発する可能性があります。
治療の終了時期は医師とよく相談することが大切です。
肺気腫
肺気腫とは、肺に多数の小さな穴が生じる病気です。
発症する方の多くが喫煙者、もしくは喫煙者の同居家族であり、原因は喫煙が深く関係しています。
肺は一度損傷すると再生されない臓器です。
そのため、肺気腫によってどんどん肺が損失すると、安静時にも息切れを起こすなど呼吸がしづらい状態になります。
症状の程度によっては酸素吸入も必要です。
肺気腫の治療方法は、まず禁煙すること。
禁煙することで肺気腫の進行を抑えられます。
その次に吸入や呼吸器リハビリなどの治療を行います。
進行することで酸素吸入が手放せない状態となり、日常生活にも大きな支障をきたすため、早めの治療が重要です。
胸水
胸水とは、肺を囲んでいる胸腔に過剰に液体が溜まる病気です。
この胸腔には肺の動きをスムーズにするため、正常な状態であっても少量の潤滑液が存在します。
しかし、心疾患やがん細胞などが原因で、胸腔に過剰に液体が増えてしまうと肺が圧迫されてしまいます。
その結果、呼吸不全の症状を引き起こす恐れがあるため注意が必要です。
胸水の治療法は、原因によって異なります。胸水を抜くと呼吸が楽になるため、胸水を抜く治療を行うこともありますが、原因によっては再発の恐れがあります。
何度も胸水を抜く治療を繰り返し行うと、身体に負担がかかり、合併症のリスクが高まるため、患者さまの状態に適した治療方法を選択することが大切です。
喀血(かっけつ)
喀血とは、肺や気道から出血する病気です。消化管から出血する「吐血」とは異なりますが、どちらの場合も口から出血することが多いため、見た目だけでは診断が困難です。喀血かどうか的確な診断を行うためにはCT撮影を行います。
喀血の原因には、肺がんや肺結核後遺症、気管支拡張症などの病気が考えられます。
治療法は、止血剤の点滴と原因となる疾患の治療です。
止血剤の点滴を用いても出血を繰り返す、多量の出血がみられる場合は、カテーテルによる治療を行います。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)
呼吸をする時に気管支や肺に障害が生じ、うまく息を吐けなくなってしまう病気です。
生活習慣病の1つであり、長年喫煙している方に発症しやすく、原因には喫煙が深く関わっているといわれています。風邪をひいていないのに咳や痰が出たり、少しの運動で息切れをしやすくなったりします。
慢性閉塞性肺疾患を放置すると、症状が悪化したり、肺機能が低下したりする恐れがあるため早期発見・早期治療が大切です。
喫煙者はリスクが高いため、気になる症状がある方は早めに受診しましょう。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)
睡眠時に呼吸が一時的に止まってしまう病気です。
「Sleep Apnea Syndrome」の略からSAS(サス)とも呼ばれています。
医学的には、10秒以上呼吸が止まっている状態が7時間の睡眠中に30回以上、もしくは1時間に5回以上起こっていると睡眠時無呼吸症候群と診断されます。
呼吸が止まることで睡眠時に酸素が不足し、心臓や脳、血管などへの負担がかかるため、心筋梗塞や高血圧、脳梗塞などの合併症を発症するリスクも高まります。

地域に寄り添い、79年。

専門医複数名
在籍

下館駅から徒歩4分
駐車場完備

土曜日
12:30まで診療
-
日本消化器外科学会 認定医,日本外科学会 認定医,日本医師会 認定産業医,日本医師会 認定健康スポーツ医 大圃 弘
-
日本外科学会 外科認定医,日本外科学会 認定登録医,日本医師会 認定産業医 大関 美穂
-
日本内科学会 認定内科医 大圃 研,根岸 良充,伊藤 洋平
茨城県筑西市にある大圃クリニックは日本内科学会 認定内科医が在籍。昇降機完備のバリアフリー。
内科から胃腸科、形成外科、皮膚科など幅広い診療科目に対応できるので、症状に応じて適切な診察が可能。下館駅北口から徒歩4分で駐車場20台完備。土曜日も診療可能です。
記事の執筆・監修者プロフィール
1946年(昭和21年)に父が『大圃外科医院』を開院し、約70年にわたり、入院・手術の出来る病院として、地域医療に取り組んで参りました。
1967年には『大圃病院』、1994年に『大圃クリニック』と名称と診療体制を変更し、今まで同様に多くの患者様にご来院いただいております。
これからも患者様一人ひとりの健康と快適な生活を支えることを最優先に考え、地域社会に寄り添った診療ができるよう身近なかかりつけ医を目指して参ります。
資格
- 日本消化器外科学会 認定医
- 日本外科学会 認定医
- 日本医師会 認定産業医






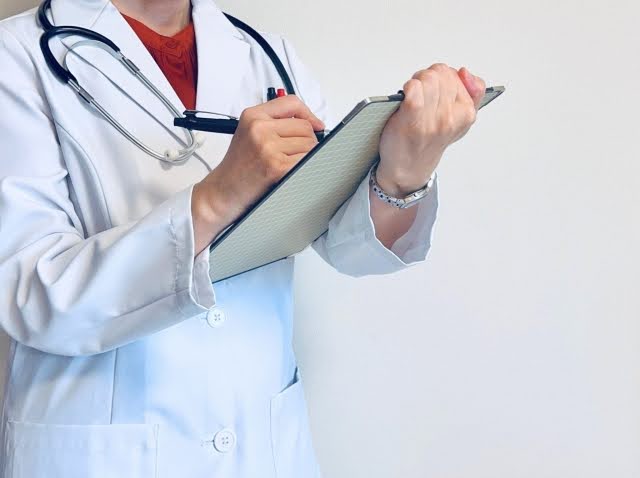
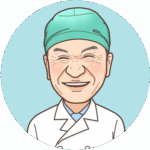


大圃クリニック院長
大圃 弘
ご自身の肺の状態を把握しておくことはあらゆる疾患の予防にもつながります。
スパイロメトリーを希望される方はお気軽に当院までお問い合わせください。